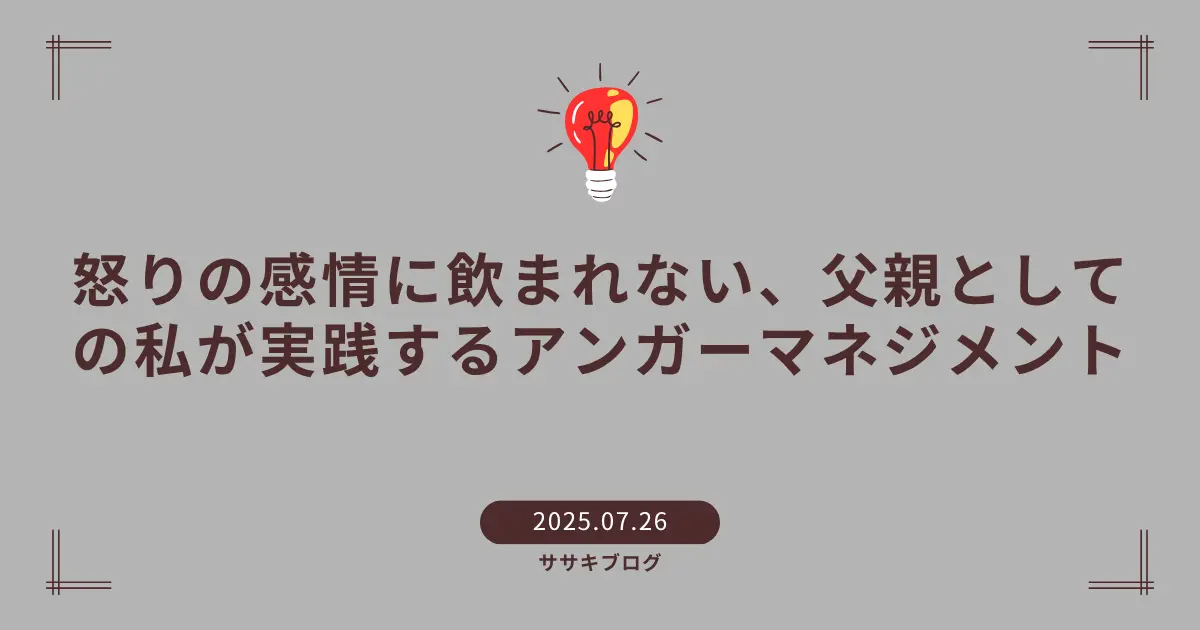“怒らない父親”じゃなくていい。でも、後悔する父親にはなりたくない
3歳の娘との、ある夜の出来事。
歯磨きを嫌がる娘に、私は何度も優しく声をかけた。だけど彼女は笑いながら逃げ回り、全然言うことを聞かない。疲れもたまっていたし、早く寝かしつけたかった私は、つい声を荒げてしまった。
「いい加減にしなさい!」
その瞬間、娘の目に涙が浮かんだ。
そのとき、娘は何も言わなかった。ただ小さく震えながら、その場に固まっていた。
普段は甘えん坊で、こちらの顔を見てニコニコする子が、あんな顔をするなんて——。
その表情が、ずっと頭から離れなかった。
その後、妻に寝かしつけをバトンタッチして、ひとりリビングで冷めたお茶を飲みながら自己嫌悪に沈んだ。
——怒りたかったわけじゃないのに、怒ってしまった。
そんな自分が情けなくて、「こんな父親でいいのか?」と自問自答していた頃、たまたま手に取ったのが『アンガーマネジメント入門』(安藤俊介 著)だった。
それは、私の「怒り」に対する見方を大きく変える一冊だった。
家庭内コミュニケーションは、その人のコミュニケーション能力の縮図——
怒りとどう向き合うかが、その人の“伝える力”を決める”
1. 怒りは“技術”でコントロールできると知った
『アンガーマネジメント入門』を読んで一番衝撃だったのは、怒りは「自分で選んでいる感情」であり、「技術でコントロールできるもの」だということだった。
それまでは、怒りは一種の“衝動”であって、自分の意思とは無関係に湧き上がるものだと思っていた。
でも、実際は違った。
怒りには明確なプロセスがある。
「出来事が起きる」→「意味づけをする」→「怒りが発生する」
つまり、怒りが生まれる前に、「その出来事をどう解釈したか」が鍵なのだ。
私の場合、「子どもは親の言うことを聞くべきだ」という無意識の価値観、いわゆる“コアビリーフ”が強く働いていた。
歯磨きを嫌がる娘を見て、「子どもは言うことを聞かないといけないのに、なぜ従わないんだ」と思っていた。
だから腹が立った。
でも、その価値観自体は、私の中の“辞書”にすぎない。
その辞書を無意識に絶対視していたからこそ、怒りが爆発したのだ。
「怒ってしまった」のではない。
私は、「怒る」という行動を、自分で選んでいたのだ。
2. 育児で活かした3つのアンガーマネジメント実践法
怒りを選んでいたと気づいた私は、「じゃあ、どうすればうまく怒りと付き合えるのか?」を考えた。
アンガーマネジメントには、実践的なテクニックがいくつかある。その中で、私が特に効果を感じたのが以下の3つだ。
ストップシンキング(思考停止)
「もうダメだ!ムカつく!」と思った瞬間、頭の中で強制的に思考を止める。
「なんでこんなことを言うんだ?」「どうしてわかってくれないんだ?」と考え始めると、感情はエスカレートするだけ。
ストップシンキングは、考えるのを“やめる”ための技術だ。
何も考えずに、まず一呼吸置く。それだけでも、冷静さが少し戻ってくる。
例えば、娘が牛乳をこぼした瞬間、「またかよ…」と怒りがこみ上げた。
でも、すぐに黙ってその場で深呼吸。
「今怒っても意味がない」とだけ思って、ティッシュを取りに行った。
何も言わなかったら、娘の方から「ごめんね」ってつぶやいた。
怒らなかったことで、謝れる空気が残っていたんだと思う。
ちなみに似たテクニックで怒りを感じてから6秒間、何も行動を起こさずにやり過ごす、「6秒ルール」もある。私にはストップシンキングの方が向いていると感じた。
タイムアウト(物理的に離れる)
どうしてもその場にいるとイライラが募ってしまうときは、「ちょっとトイレ行ってくるね」と言って数分離れる。
ほんの30秒でも、物理的な距離が感情のリセットに効果的だった。
私は、子どもと向き合い続けることが“父親としての責任”だと思い込んでいたけれど、時には離れることも“誠実な対応”だと知った。
例えば、寝かしつけ前の時間、娘がYouTubeをやめたがらず、つい「いい加減にしなさい」と声を荒らげそうになった。
でもそのとき、「ちょっとだけ飲み物取ってくるね」と言って、台所に避難。
30秒だけだったが、その間に気持ちが整理できた。
戻ったとき、「そろそろ寝る時間だよ」と普通に声をかけられた自分に驚いた。
娘も、「わかった」と言ってタブレットを閉じてくれた。
そのとき、「怒鳴るより離れる方がずっと建設的だ」と確信した。
コーピングマントラ(自分に言い聞かせる)
怒りがこみ上げたとき、自分に言い聞かせるフレーズを決めておく。
私の場合は、「今、怒っても解決しない」「大事なのは関係性」と心の中で唱えるようにした。
これは自己暗示のようなものだけど、感情を鎮めるのに効果的だ。
怒りの波が静まるまでの“アンカー”になる。
例えば、朝の支度中。
「早くして」と何度も言ってるのに、娘が靴下すら履こうとしない。
苛立ちがピークになりかけたその瞬間、「今、怒っても解決しない」「大事なのは関係性」と、コーピングマントラを唱えた。
不思議なことに、気持ちがすっと落ち着いて、「手伝おうか?」と自然に声をかけられた。
すると娘も、少し照れくさそうに「うん」とうなずいた。
怒らなかったことで、時間はちょっとかかったけれど、朝の雰囲気はとても穏やかだった。
3. 怒りを「伝えたい感情」に変換する
怒りの奥には、実は「本当に伝えたい感情」があると、著書には書かれていた。
私が娘に怒鳴ってしまった夜、伝えたかったのは「歯磨きしてほしい」だけじゃない。
「パパも疲れているんだよ」「今日は早く寝てくれたら嬉しいな」という、弱さや願いだった。
怒鳴る代わりに、
「いい加減にしなさい!」ではなく、
「静かにしてくれると、パパ嬉しいな」と伝えた方が、はるかに効果的だし、関係性も傷つかない。
子どもは、親の感情をものすごく敏感に感じ取る。
だからこそ、私の怒りがそのまま「怖い人」として伝わってしまうのではなく、「伝えたいこと」に変換して届ける努力が必要なんだと実感した。
今では「怒りのセリフ」を「お願い+気持ち」に置き換える練習をしている。
たとえば、
・「うるさい!」 → 「静かにしてくれると嬉しいな」
・「早くしなさい!」 → 「早くしてくれると助かるよ」
・「何回言ったらわかるの!」 → 「1回で伝わると、パパはすごく助かるんだけどな」
こうして言い換えると、娘も「ニコッ」と笑ってくれることが増えた。
4. 「父親だからこそ」アンガーマネジメントが必要だと思う理由
男性は女性に比べて、怒りを外に出しやすいと言われている。
実際、私自身、感情の調整が苦手だと感じる。
「疲れてる」「うまくいかない」「わかってもらえない」
そうした感情が積もり、爆発する。だけどそれは、自分にも周囲にもダメージを与えるだけだった。
アンガーマネジメントを知ってからは、感情の“途中経過”に気づけるようになった。
「あ、今、自分は苛立ち始めてるな」
「これ以上はまずいな」
そんな“前兆”をキャッチできるようになっただけで、衝動的に怒鳴ることが激減した。
結果として、娘との関係も変わった。
怒るよりも、「どう伝えるか」「どう距離を取るか」に意識を向けられるようになり、娘とのコミュニケーションの幅も広がった気がする。
怒らない父親ではなく、怒りと向き合える父親を目指すこと。
それが今の私のテーマだ。
完璧な父親じゃなくてもいい。
でも、「怒ってばかりの父親」には、なりたくない。
その思いだけは、これからも忘れずにいたい。
まとめ
育児は感情との闘いだ。
そして、怒りという感情は、決して「悪」ではない。
ただ、それに飲まれてしまうと、自分も周りも傷つく。
だからこそ、アンガーマネジメントという技術が必要だ。
怒りをゼロにすることはできない。
でも、怒りとうまく付き合う技術を身につければ、育児も、家庭も、少しずつ変わっていく。
これは完璧な解決策じゃない。
でも、怒りに後悔しなくなるというだけでも、育児がぐっとラクになる。
だからこそ、私はこう考えるようになった。
私は「家庭内コミュニケーションは、その人のコミュニケーション能力の縮図——」と考える。
あなたは、自分の怒りとどう向き合っていますか?
家庭の中で、どんな言葉を届けたいと願っていますか?